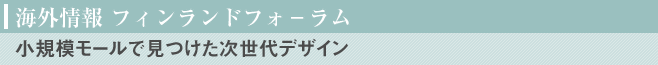|
ヘルシンキデザインキャピタル 続報
今年はヘルシンキが、2年に一度のデザインキャピタルに選ばれました。フィンランドデザインがさらに世界へ広がることを祈って、大きな期待を抱きながら、ヘルシンキデザインキャピタルの年が明けました。 街を歩けば、ヘルシンキデザインキャピタルのロゴとポスターを見かけます。
 |
(写真左) 大聖堂での年明けイベントは、大胆にも、大聖堂のファサードに動画を映し、大音量ミュージックと共に来るべきフィンランドデザインの成功を祈りつつ、新年を迎えました。
(写真右) ヘルシンキ市は公共ゴミ箱にもデザインキャピタルのロゴを入れて、ヘルシンキのイメージをデザインと結び付けようとしています。この写真はヘルシンキ地下鉄ブオサーリ駅前のゴミ箱。
|
|
|
ポスターに描かれた様々な形象は、デザインに対する考え方が、人それぞれに異なっているということを意味しています。デザインも芸術と同様、各人が好きなように理解してください。
 |
(写真左) ヘルシンキデザインキャピタルのリーフレット、カバーデザイン
(写真右) 折りたたみのリーフレット写真と統一ポスター
|
|
|
多くの企業もスポンサーとして、年間のデザインプロジェクトをサポートしています。ノキアもデザインキャピタルのロゴを使うことで企業イメージのアップを図っています。
ヘルシンキデザインキャピタルは、デザインの領域を拡大させて、人々の生活の質を向上させる。Nokiaもその一端に仲間入りして、これからのデザインの意味を一層広げていくでしょう。
今年のデザインキャピタルのイベントには、ヘルシンキ以外の都市も便乗しています。ヘルシンキの北方100キロにあるラハティ市もその一つで、色々なイベントが開催されています。
もともとラハティ市は、2年に一度、「木を愛する」ことで世界的に活躍する建築家やデザイナー、作家に、“SPIRIT OF NATURE”賞を授与しています。いかにもフィンランドからの発想をイメージ化したデザインが選ばれます。日本からは建築家の隈研吾氏が2002年に受賞しました。受賞した作家がデザインした作品を街の中に残し、ラハティ市の都市計画の一環として永く高く評価されていくでしょう。
 |
(写真左) 隈研吾氏がデザインしたタクシー乗り場のベンチ。
ラハティ湖畔に建つシベリウスコンサート・ホール前に設置されたもので【T】を形取ったデザイン。
(写真右) 2000年に受賞したイタリアの著名建築家レンゾ・ピアノ氏デザインによる湖畔の木造カフェ。
これもラハティ市の名誉ある思い出として街の風景になっている。
|
|
|
クルーヴィのトイレは目からウロコの発想でした。いま、日本の小中学校では男子小便器を使う子が少ないらしい。一方、フィンランドの子どもたちは森林とサマーコテージの自然トイレで、環境の循環を体得すると聞きます。
たとえば、東京駅の中にこんなトイレがあれば、清掃時の行列が緩和されるので、少なくとも女性には好評かもしれません。ちょっとした不安と緊張感は、ユニバーサル&エコ、ジェンダーフリーの考え方に慣れていけば、次第に解消されていくでしょうか。
さて、フィンランドのデザインから社会生活の情報を聞くにつけて、ひとつの問いかけが生まれてきました。
【質問】 ヨーロッパ人のインテリアへの感覚はどのように培われるのでしょうか。小さい頃から考えたり、自分で行動を起こしたりする機会が豊富なのでしょうか。日本では、家庭科(生活科)の授業で衣食住の衣と食を教える先生はいるが、住を教える先生がいない。これが「住」への無関心を呼んでいると、建築関係者からも問題視されるようになって来ました。ある食品会社は、幼児期の刷り込みが重要ととらえて、全国の幼稚園を回って食育イベントを開催していますが、住関連企業でそのような事業を行う会社は無いのが日本の実情です…。
さあ、クールフィンランド、ホットフィンランド、デザインキャピタル…。次回は『住』に関する基礎教育についてもリポートしていただきましょう。
(せきゆうこ・フィンランドフォーラム・コーディネーター)
|