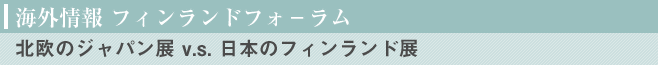|
デザインの現状と展望 スロウライフデザインへ
今日のフィンランドでは、「デザイン」という言葉がマーケティングや販売促進の用語としても幅広く使われるようになりました。本来の意味を失ったかと思うほどです。企業もコピーライターたちも、「デザイン」という言葉のもつ好印象が売り上げにつながることを意識して、濫用する傾向にあります。
そもそも、デザインとはその製品を生産する企業の戦略を語るものです。フィンランドの近代産業の発展期には【デザイン】が国家レベルで重要な役割を果たして、成功を導きました。21世紀の文化、情報、経済の潮流の変化と共に、これからのデザインは、社会の中での穏やかな暮らし方への配慮、つまり【スロウライフ】が最大の課題になると思います。
私たちはデザインに絶対的な評価を下す必要はありません。デザインとは、「誰が、どのような視点から見るか?」により、評価が異なるものです。個人の評価は、個人の感性によります。良い印象が残る時には、デザインがその目的を達成したと考えることができます。しかし、見た目に優れたフォルムだと感じられても、使いにくいとか、読みにくいなどの機能的な理由で不愉快な思いが残れば、それは、デザインの質を落とすことになりかねません。
『消費者中心主義』で生産される製品は、メーカーのロゴがなければどれも似たような印象です。似たりよったりの商品が氾濫する現状は、私たち自身が周りの環境に対して無関心、時には、無責任になるという状況に至ります。まず、メーカーは生産者としての個性を発揮するデザインにより、消費者それぞれの主体的な判断にゆだねられるような商品を開発するべきだと思います。今日の加速度的な競争社会の中で、個性や斬新さ、品質までもが失われ、さらに、何を目的として製品を作っているのかと疑問に感じることさえあります。じっくりと考慮し、思索を重ね、美的なデザインに仕上げる時間が足りないのでしょうか。質の低いデザイン・アイテムが集まると、日常生活面での嫌悪感を増幅するだけでなく、技術的なエラーを引き起こすことがあります。読みにくい計測文字で操縦者がミスを重ねれば、デザインの悪さからリコール問題に発展することも現実でしょう。
エネルギーの浪費とゴミの増大により、私たちの社会はかつてない代償を負っています。デザイン面の考慮不足から製品寿命が短くなれば、現代社会の目指す条件に満たなくなります。これは社会的な問題です。
今日、環境や製品の生産プロセスに関する情報が開示されるにつれて、デザインを評価する方法が変わりつつあることは幸いです。人々が製品に関するバリューチェーンをよく理解し、社会や環境への責任感が重要視されるにつれて、デザインのコンセプトが新たな姿に生まれ変わっていくでしょう。すなわち、生活の質は物質的なものの数量ではなく、地球共同体の一部として評価されます。そのためにデザインの根本をいかに考えていくか。その分岐点に立っていると思います。
こうして時々ですが、フィンランドから日本を訪問すると、さまざまなことに考えが及びます。そして初めは人の多さに圧倒されますが、じきに慣れてくると、おいしい食べ物や素晴らしい美術館に囲まれる環境に感謝したいと思うようになります。
2011年もフィンランドのデザインをご紹介することで、日本の読者の皆様と交流していきたいと思います。お元気で。
|